カテゴリー分かりやすく4つに分けたよ!

「指を鳴らすのがクセ」
「膝や肩がポキッと鳴るのが気になる」
そんな経験、一度はあるんじゃないでしょうか?
なんか、関節を鳴らすと少し気持ちいい感じがしますもんね。
理学療法士として働いている中でも、「この音って体に悪いんですか?」という質問をよく受けます。
結論から言えば、音がするだけで痛みや機能障害がないなら、基本的には問題ありません。
でも、中には「危険なサイン」として注意すべき音もあるんです。
この記事では、そんな「関節が鳴る音」のメカニズムや、気にしなくていい音・気にした方がいい音の違いについて、分かりやすく解説していきます!
・骨をポキポキ鳴らしている人
・関節に痛みがある人
・関節の音が鳴りやすい人
⸻
1.そもそも、なんで関節は音が鳴るの?
よく言われるのが「関節の中で気泡が弾けて音がする」という説。
確かに関節内には**滑液(かつえき)という潤滑液が存在していて、その中に溶けたガス(二酸化炭素など)**が含まれています。
関節を引っ張ったり、強く曲げ伸ばししたりすると、関節包(関節を包んでいる袋)の中の圧力が一時的に下がります。
このとき…
圧力の低下によって
滑液内のガスが急激に気泡として現れ、
そのときに「ポキッ」と音が鳴る
この現象は「キャビテーション(cavitation)」と呼ばれています。
意外かもしれませんが、音の正体は「気泡が弾ける音」ではなく、「気泡ができる音」なんです。

あれ?骨が鳴ってるわけじゃないんだ!
身体に詳しい人も気泡ができる音って言ってたよ!
⸻
2.実際に証明された?
2015年、カナダのGreg Kawchukらの研究チームがMRIを使って、関節が鳴る瞬間をリアルタイムで観察しました。
その結果、音が鳴るタイミングで関節内に気泡が出現する様子が確認され、
「気泡が弾ける音」ではなく「気泡が生まれる音」であることが明らかになりました。
○参考文献
Kawchuk GN, Fryer J, Jaremko JL, Zeng H, Rowe L, Thompson R (2015) Real-Time Visualization of Joint Cavitation. PLoS ONE 10(4): e0119470. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119470
⸻
3.なぜ何度も鳴らせないの?
一度鳴らした関節は、しばらくするともう音が鳴らなくなりますよね。
これは、気泡ができた状態がしばらく続くためです。
• 数分〜20分ほど経つと、気泡は再び滑液に溶け込みます。
• それによって再び圧力変化が起きやすくなり、また音が鳴る状態になる。
つまり、「連続で鳴らせない」のは、ちゃんとした物理現象による自然な反応なんですね。

関節の中の気泡って炭酸の作り方に似てるね!
⸻
4.音が鳴る=悪いこと?
ここが多くの人が気になるポイントだと思います。
結論としては、
つまり、「クセで鳴らしてしまう」程度であれば、そこまで神経質になる必要はありません。

よく骨を鳴らす癖があったから、少し安心したなぁ。
皆んなに骨が縮むよって脅されてたもんな。
⸻
以下のような症状を伴う「音」は、何かしらの問題を抱えている可能性があります。
● 痛みを伴うポキポキ音
⇒ 関節内での摩擦や、炎症、半月板や靱帯の損傷の可能性あり
● 引っかかるような音と動作制限
⇒ 腱や靱帯が関節構造に引っかかっている(スナッピング症候群など)
● 高齢者の関節で頻繁に鳴るガリガリ音
⇒ 軟骨のすり減りによる変形性関節症の可能性
● 肩甲骨まわりで「ゴリゴリ」「ザラザラ」鳴る音
⇒ **肩甲胸郭関節のスナッピングスキャプラ(snapping scapula)**の可能性あり
肩甲骨と肋骨の間にある滑液包や筋膜の滑走性が低下することで、動くたびに摩擦音が発生します。
痛みがなければ問題は少ないですが、前鋸筋・肩甲下筋・大胸筋などの柔軟性や滑走性の低下が関与していることが多く、
気になる場合は理学療法士などによる評価・施術が有効です。
こういった場合には、自己判断せず、整形外科や理学療法士などの専門家に相談するのがおすすめです。
4.さいごに
内容を簡単にまとめると
「関節が鳴るのってなんか怖い…」と思っていた方も、
仕組みを知ることで少し安心できたんじゃないでしょうか?
体の小さなサインを見逃さず、必要以上に不安にならず、
でも大事な兆候は見逃さない。
そんなバランス感覚が、健康な体づくりには欠かせません。
もしこの内容が参考になったら、ぜひ周りの方にもシェアしてみてくださいね!

身体の不安が取れるとなんだか気分が軽くなるよね!けど、変な音が関節になる時は要注意だね!

この記事が気に入ったら
フォローをお願いします!
私がこの記事を書いたよ!
yushi-k1 男性
幼少期からサッカーを続ける→身体への興味が湧き理学療法士の道へ→総合病院に勤務→訪問リハビリへ転職|一般の方々の身体についての興味や知識の少なさに驚愕/低給料で十分な学びが得られない→心と身体の一般的な知識の共有、副収入を目的にブログを開設|心身共に健康的な生活を送ることができるような情報と良質な商品の紹介を発信していきたいと思います!●所有資格/理学療法士/JADP認定メンタル心理カウンセラー®︎







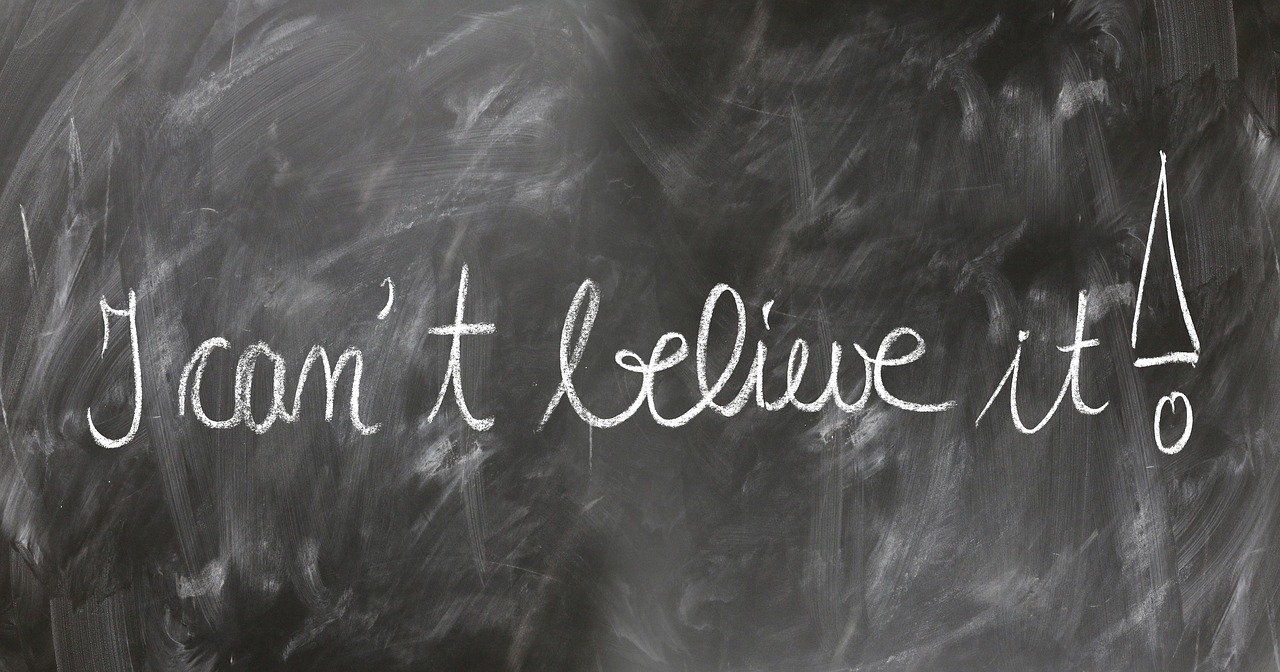




コメントを書く