- 2022年5月8日
【理学療法士向け】この関節の硬さは拘縮?短縮?癒着?関節可動域制限となる関節拘縮のまとめ!!
突然ですが、あなたは拘縮と短縮の違いをしっかりと説明できますか? それぞれに効果的なアプローチをかけられるでしょうか? ……
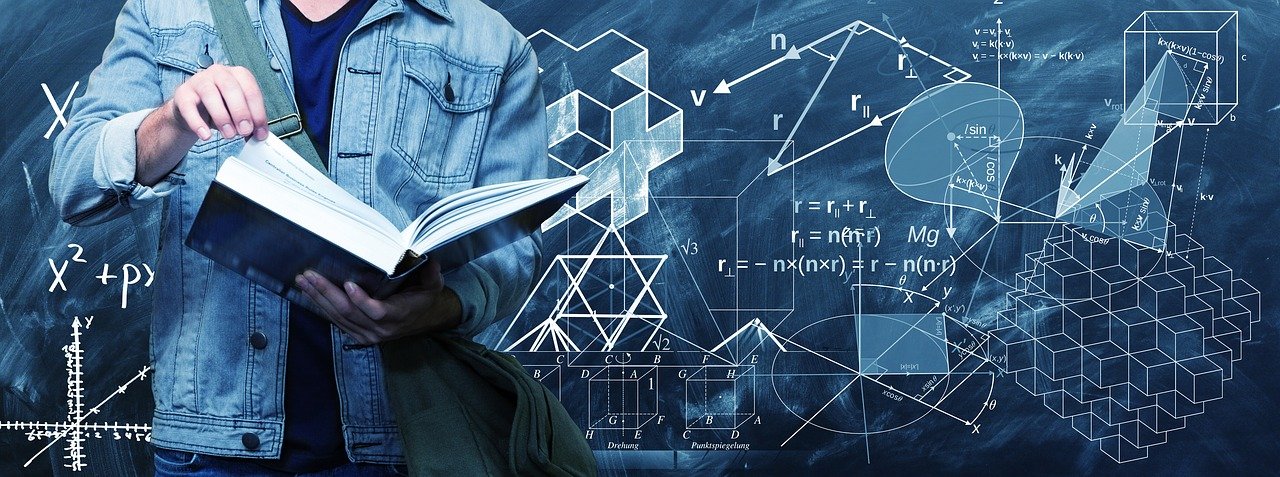
バイオメカニクスとは『生体力学』と呼ばれる分野になります。
地球上に生きる生物は全て重力下で運動をおこなっているため、身体は力学の法則に基づいて運動しているということになります。
動きの専門家である私たちセラピストは必ず理解しないといけない分野だと思います。
これらの知識の基礎は物理学なのですが、高校で物理を履修していなかった方には難しい内容になってしまうことでしょう。
ここでバイオメカニクスでの力学的法則をまとめていきます。
今一度、バイオメカニクスについて復習していきましょう!

地球上に存在する生物にかかる外力は重力、床反力、慣性力、空気などの抵抗、電磁力などがあります。
重力は誰にでも働く、地球上で働く普遍的な力であり、常に鉛直下向きに引っ張る方向に力を加えます。
重力から逃れることはできず、地球上の生物は皆、重力を利用して運動しているといいます。
重力は重心に作用し、重心がずれると重力によって働く力が大きく変わってきます。
サイコロが転がっていくのは重力が重心を大きく超えるから転がっていきます。
坂道を物体が転がっていくのは常に重力が重心を超えるからです。
力の方程式はF=maであり、この公式は非常に大切な公式です。
これが力学の基本になります。
FがForceで力で、mはmassで質量、aはaccelerationで加速度です。
人間が力を操るには質量は普遍であるため、加速度を操作する必要があります。
つまり物体の重さは変えることができないので、動かすということです。
質量が決まっていれば、加速度を変化させることで力を変化させることができます。
もし、身体への負担を抑えたいのであれば、人間が簡単に操作することができる加速度というものに目を向けるべきだと言えますね。
慣性モーメントとは回転運動のしづらさ、回転の止まりづらさを表しています。
公式は
I=mr^2
公式から分かるように例え質量が同じであっても、半径が大きいと慣性モーメントは簡単に大きくなってしまうのです。
慣性モーメントは回転半径の影響が大きいことが見て分かりますね。
コマを想像してください。
小さいコマと大きなコマを回すときはどちらの方が回すときに大変ですか?
絶対大きいコマを回す時ですよね!
身体に当てはめて考えると腕を回す時、腕を伸ばしながら回すのと曲げながら回すのでは使用する力量に大きな差が生じます。
慣性モーメントが大きければ大きいほど、動かす時と止める時に大きな力が必要になってしまうので、身体に当てはめて考えた時に負荷が大きくなってしまうことが想像できますね!
胸郭は特に質量が大きく回転半径の影響を強く受ける部位です。
胸郭のモビリティーが低いと、回転半径は大きくなり、結果的に慣性モーメントが大きくなるのでとても扱いづらい部位になってしまいます。
逆にモビリティーが高いと、撓む様な形になるので回転半径が小さくなり、慣性モーメントを大きく減らすことが可能になります。
人の動きを効率的に動かすためには慣性モーメントを考えて、できるだけ回転半径を小さくする必要がありますね!
角運動量保存則とは外力が働かなければ角運動量は一定に保たれるというものです。
簡単に言うと回転していない物体は無回転を維持し、外力が何も働かなければ回転している物体は回転し続けるということです。
角運動量を表す公式は
L=Iω
角運動量は回転する物体の重さと回転半径と回転の速さで決まります。
角運動量保存則を簡単に体感することができる方法があります。
車輪付きの椅子に膝立ちをして体幹を回してみましょう!
体幹は回ろうとしますが、下肢は逆に回ろうとして体幹の回転を打ち消す方向に動いてくるのです。
上半身だけを動かすのは絶対に無理です!
結果、無回転を維持するのです。
では、この法則がどういった場面で働くのでしょう。
想像して欲しいのは、テニスでラケットを使ってボールを打つ時、野球でバットを使ってボールを打つ時などです。
バッティング動作では身体の回旋が非常に大切な動きになりますね。
バッティング動作で身体を捻って、力をボールに伝えますよね?
この上半身の回旋には角運動量保存の法則が働き下半身にも同等の角運動量のエネルギーが加わります。
相当な質量と速さで動くわけですから下半身にかかるストレスも相当なものでしょう。
上半身で生じた角運動量を下半身で打ち消さなければなりません。
そのエネルギーに耐えきれない下半身であれば怪我のリスクが大きく高まってしまうことでしょう!
徐々に力が蓄積されていき、上限を超えると身体は壊れていってしまうのです。
上半身を支える下半身の影響は強大ってことが分かりますね。
下半身が出来上がってないのに、無理に上半身だけトレーニングしていても怪我のリスクを高めるだけなので注意が必要です!
関節合力とは関節にかかる総合力のことをいいます。
片足立ちを例にすると体重40キロの場合、足関節にかかる関節合力は
モーメントの公式から考えると
つま先から足関節まで40kg×15cm
踵から足関節までF×5cm
そこからF=120となります。
そうなると120+40で合計160kgもの力が足関節にかかることになります。
実際は体重以上の力が関節にかかっていることが関節合力を踏まえて考えると理解することができますね。
また、関節合力は筋活動の協働収縮系に支えられています。
肘を曲げる時にかかる筋肉への負担を考えると
肘屈曲10kg 伸展0kgでなく
肘屈曲20kg 伸展10kgとなります。
必ず主動作筋が働くと拮抗筋が働き、関節の安定性を作っていることが分かりますね。
どちらかが上手く働かないと、途端に関節の安定性は失われ、機能が低下してしまいます。
肩関節での不安定感、膝関節での不安定感を訴える患者さんが多いと思いますが、主動作筋と拮抗筋のバランスはどうかをもう一度評価してみたいですね!
|
参考図書はこちら↓
|
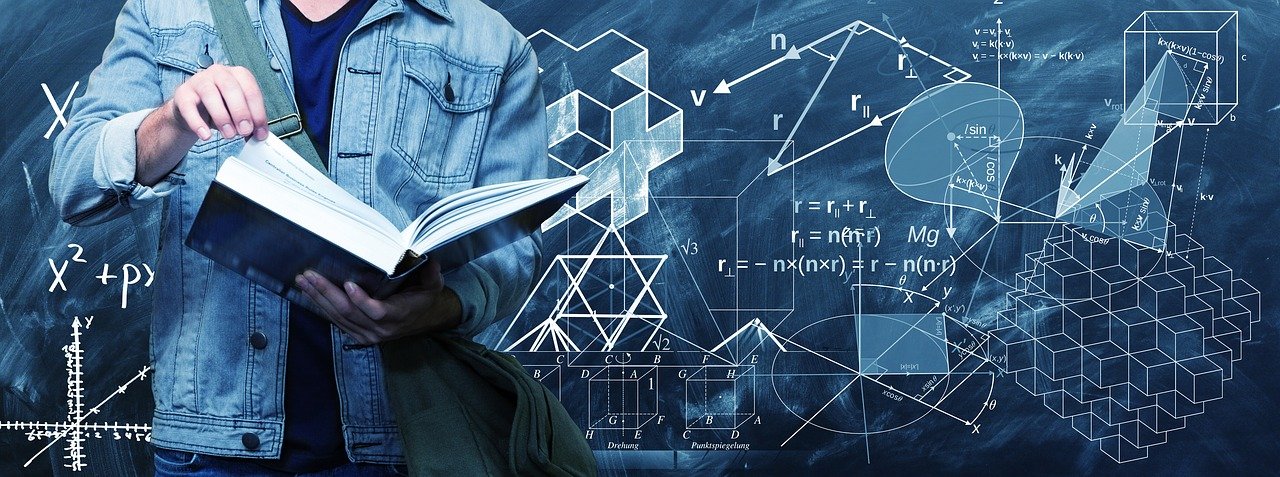
幼少期からサッカーを続ける→身体への興味が湧き理学療法士の道へ→総合病院に勤務→訪問リハビリへ転職|一般の方々の身体についての興味や知識の少なさに驚愕/低給料で十分な学びが得られない→心と身体の一般的な知識の共有、副収入を目的にブログを開設|心身共に健康的な生活を送ることができるような情報と良質な商品の紹介を発信していきたいと思います!●所有資格/理学療法士/JADP認定メンタル心理カウンセラー®︎
コメントを書く