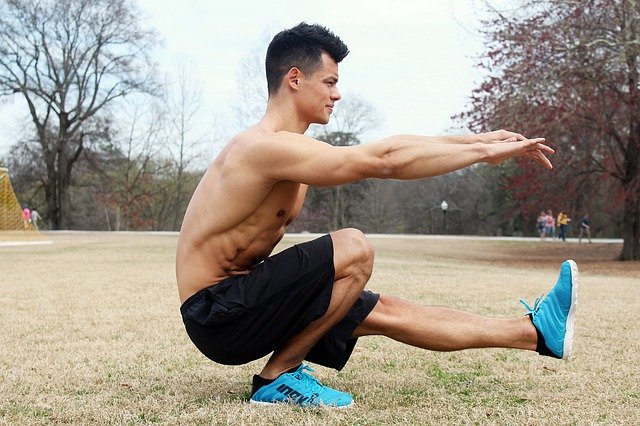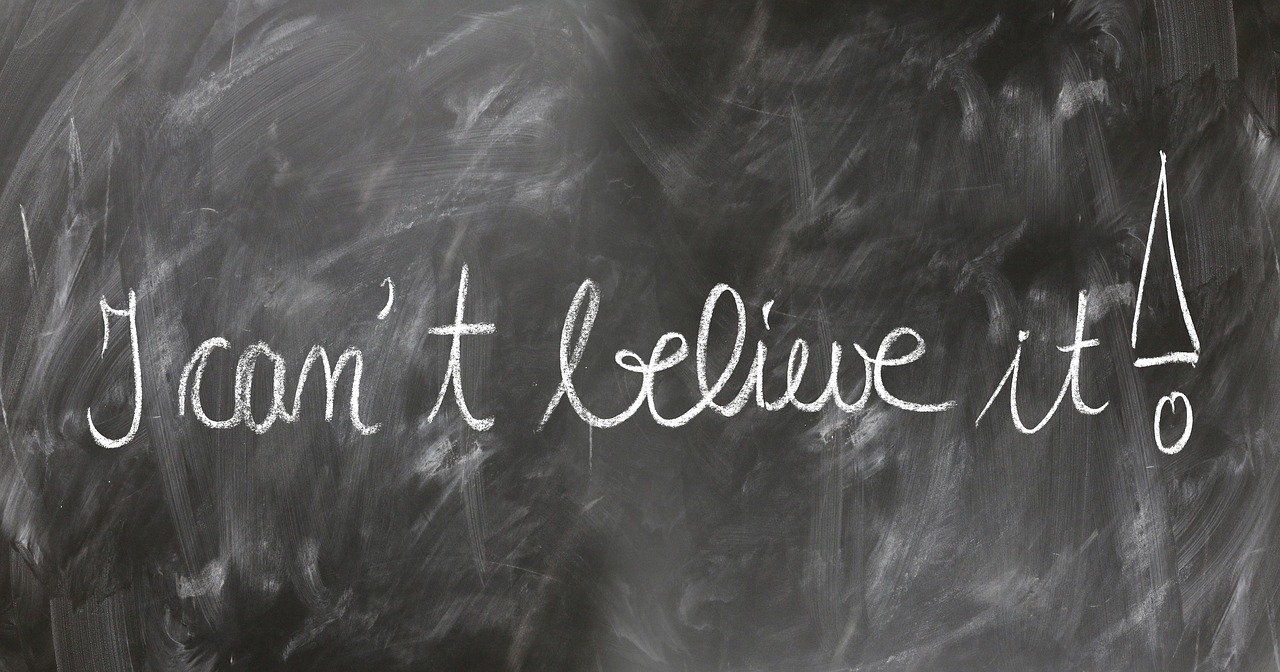カテゴリー分かりやすく4つに分けたよ!
理学療法士向け category
【理学療法士向け】関節拘縮の解剖学的背景と予防方法:理学療法士が知るべきポイント!
普段、働いていると拘縮って言葉は必ず聞くことがあると思います。よく聞くからこそ、……
【理学療法士向け】理学療法士こそブログを書こう!— 知識を深め、アウトプット力を高める方法 —
「なんか最近、流れ作業でリハビリしてしまっているな…」 「何も考えずにリハ……
【ブログ作成方法】初心者向け!!エックスサーバーでブログを始める手順を分かりやすく解説!
「ブログを始めたいけど、どうやってサーバーを契約するの?」 「エックスサー……
【理学療法士の話】理学療法士が知っておきたい「柔軟性」「可撓性」「弾性」の違い
理学療法の現場では、「柔軟性」「可撓性」「弾性」といった言葉を耳にすることが多い……
【リハビリの話】深部組織ー筋膜リリース(DTMR®︎)についてまとめてみた!
こんにちは! 今回は深部組織ー筋膜リリース(DTMR®︎)という手技についてまと……
【リハビリの話】訪問リハビリで新規獲得の営業で意識したいたった一つのポイント!!
理学療法士として働く中で、病院で働いていれば特に営業をする機会はなく、ただリハビ……
【理学療法士向け】ReaLine®︎について簡単にまとめてみた!
今回は日本健康予防医学会が提唱する治療理論「リアライン・コンセプト」についてまと……